
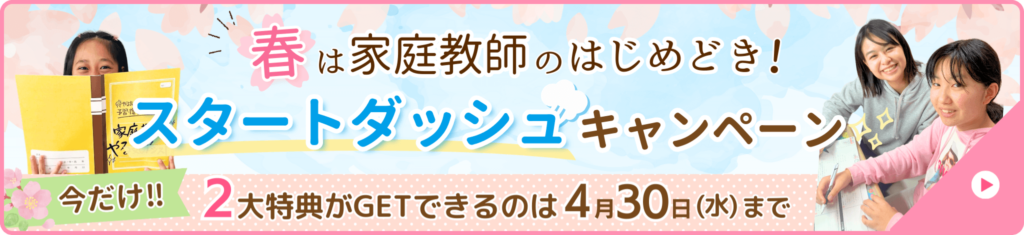





この記事は以下のサイトを参考にしています。
https://www.pref.nara.jp/secure/291704/kateigakusyunotebiki.pdf
奈良県は「家庭教育はすべての教育の出発点」として、家庭学習を推奨しています。
家庭教育は、おこさんが家族との触れ合いを通して、基本的な生活習慣や生活能力、豊かな心やたくましく生きる力などをはぐくむ、「すべての教育の出発点」です。
お子さんが毎日家庭学習を続けるためには、何よりもまず家庭での生活リズムが整っていることが大切です。「早寝、早起き、朝ごはん」など規則正しい生活を心がけ、心身ともに元気に過ごせるようにしましょう。
決まった時期に落ち着いた場所で勉強するお子さんの方が、学力が高い傾向にあります。お子さんが勉強する場所に、学習に集中できないようなものがあれば片付け、勉強している時間はテレビをつけないなど、お子さんが勉強に集中できる環境をつくりましょう。
保護者さまがお子さんに対して「こうしてほしい」と思ったことができたら褒め、できなかったら叱るといった、保護者さまの考え方を押し付けるだけでは、自分で考えて行動する力が身に付きません。お子さんは自分が努力したり工夫したりしたことを「認めてほしい」と思うものです。まずはお子さんの変容を見逃さず、見守ることを大切にしましょう。そしてお子さんの頑張りを認め、具体的な言葉で励ましましょう。
「今日は何をならったの?」と聞くことからお子さんの復習が始まります。保護者さまがお子さんの学びに関心をもつことで、自分のことを見てくれているという安心感を与えます。また、思春期のお子さんには、人生の先輩として経験を語るなど、保護者さまの適切なアドバイスが、お子さんの健やかな成長につながります。
学校で学んだことを、普段の生活の中で生かしたり、自然や文化財など本物にふれたりする機会をもちましょう。お子さんの知的好奇心が高まり、「生きて働く知識」がはぐくまれます。また、お手伝いを習慣づけ、家族のために自分のできることをやり遂げる態度を育むことは、大人になってからも、自分の仕事に責任を持つ態度を育てることにつながります。
小学校1,2年生のお子さんは習慣をつけることが第一です。毎日決まった時間に机に向かって、宿題をする習慣を身につけましょう。
勉強やお手伝いをして家族から褒められたり、家族が喜ぶ姿を見たりして、お子さんは家族の役に立ったことや自分の成長を実感し、学ぶことやお手伝いをすることに喜びを感じます。その喜びが、次もやってみようという意欲につながります。まずはお子さんのそばについて、お子さんの頑張りをしっかりと認めたり褒めたりして、お子さんの意欲を高め、習慣となるようにしましょう。
小学校3,4年生のお子さんは自主性を重んじることが大切です。自分から進んで宿題に取り組みましょう。
お子さんは、自分が頑張ったことを認められたり褒められたりすることで、自分の良さに気づき、自身をもちます。そのためにも、お子さんの良いところやお子さんが何かをやり遂げようと自分なりに頑張ったことを心から認め、褒めることが大切です。
大人になり、さまざまな苦難にぶつかったとき、子供の時に認め褒められた経験が、生涯にわたり心の支えとなります。
小学校5,6年生のお子さんは自分で計画を立てることが大切です。いつ、何を、どのように勉強するのか、自分で考えて学習しましょう。
心と体の成長とともに、お子さんは自分で考え、行動しようとする傾向が見られるようになります。一方で、相手やまわりのことを考えず、自分勝手なふるまいをしてしまうこともあります。お子さんの自主的な行動を認めるとともに、その行動の影響などをお子さんが考えられるようにアドバイスをすることが大切です。
中学生のお子さんは目的を見つけて、努力の計画を立てていくことが大切です。将来の目標に向け、自分に合った学習計画を立て、こつこつとやり遂げましょう。
お子さんに任せるという姿勢が、自分で考えようという力を育てることにつながります。お子さんの力や判断を信じて見守ることが大切です。この時期だからこそ、家族のふれあいの時間を大切にし、意識して家族で会話をする時間をつくることで、お子さんの思いや考えに気づき、しっかりと受け止め、その行動を見守り支えていきましょう。
今回は奈良県が推奨する家庭学習の手引について紹介してきました。
家庭学習は塾や家庭教師よりも大切な勉強になってくると思います。私たちも最終的にはお子さんが一人で勉強ができるようにサポートしていくことを第一目標に指導に当たっています。
家庭教師のやる気アシストは奈良県で「定期テストや入試・受験対策に強い」家庭教師として、小学1年生から高校3年生のお子さんを対象に、ご自宅に伺い勉強の指導を行っています。
少しでも興味を持って下さった方はこのページをご覧いただけますと幸いです。