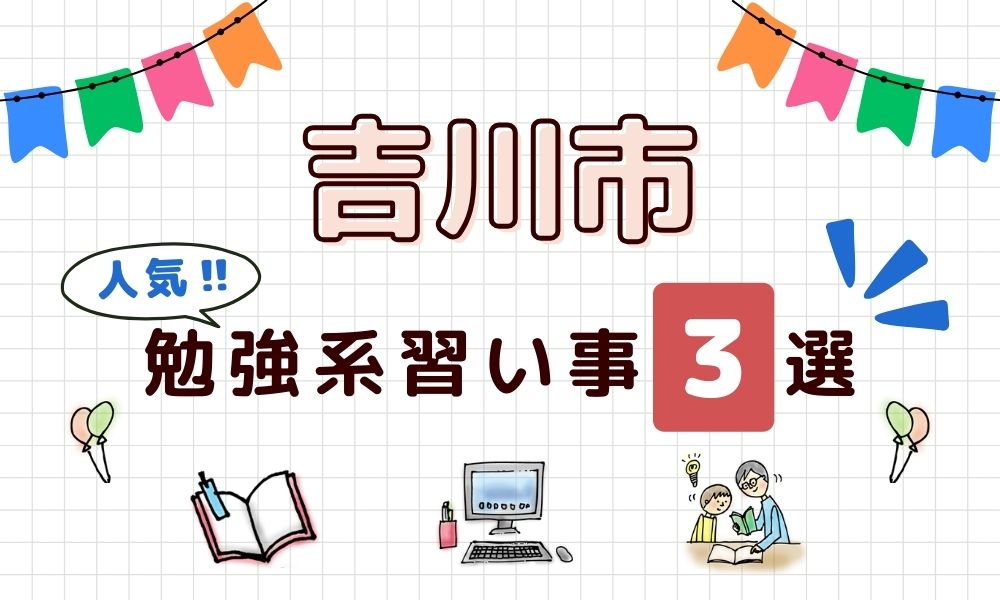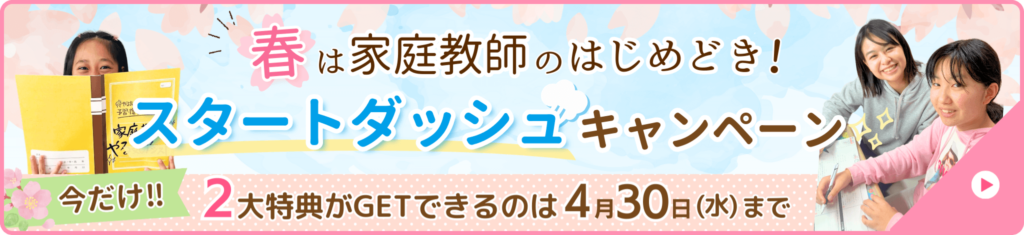





この記事は以下のサイトを参考にしています。
https://www.city.okayama.jp/shisei/0000012002.html
https://www.city.okayama.jp/shisei/cmsfiles/contents/0000011/12000/mihiraki.pdf
https://okayama-life.jp/sp/school/policy/
現代の子ども達の教育に必要な資質は、豊かな人間性とさまざまな人と共存できるように自分自身を確立していく力です。
特にこれからの社会はさらに変化が激しく予測が難しい時代が想定されるので、自分自身の力で課題を解決することや、情報を活用し自分で表現できる力が必要とされます。そのような「子どもの自立」に着目し実際に取り組んでいるのが岡山市中区です。
岡山市では市民協働で独自の「岡山っ子育成条例」を制定しています。本記事では「岡山っ子育成条例」の行動指針や岡山市が取り組んでいる事業について詳しく解説していきます。
岡山市では、豊かな人間性を身につけ、自分を高め、共に共存できるように自分自身を確立していく「自立に向かって成長する子ども」の育成に赴きをおいています。
岡山市が考える「自立」とは「自らの個性を磨き、選択と挑戦を繰り返すこと」です。
ここで岡山市が実際に取り組んでいる教育の特徴について記載した一覧表をご覧ください。
| 教育の特徴 | 取組の目的と内容 |
| ①「縦のつながり」 岡山型一貫教育 | 中一ギャップの軽減を図ることが目的。 小中と教職員が互いの授業や保育を見合い子どもの実態をもとにして同じ方向性で教育を進めるための取組を行う。 |
| ②「横のつながり」 地域と一体となって子どもを育てる「岡山市地域協働学校」 | 全ての岡山市立学校で、保護者や地域住民が学校運営に参画し、地域ぐるみで子どもの育ちを支えるため協議を行う。 (例)公民館などで地域住民が子どもの学習支援を行う「地域未来塾」など。 |
このように岡山市では、就学前から中学、高校までの縦のつながりと地域との横のつながりの中で「自立に向かって成長する子ども」を育成しています。
「岡山っ子育成条例(岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例)」は、平成19年4月1日に施行されました。
岡山市育成条例の目的は、子ども達が愛されていると実感できる家庭・学校園・地域社会を実現し、市民協議で「自立に向かって成長する子ども(自立する子ども)を育成することにあります。
岡山っこ育成条例は「子どもの自立」に赴きをおいて作成された条例であることが理解できます。
岡山市育成条例を有効に活かすためには、行動計画や行動指針が必要となります。
行動指針は、市民それぞれの立場でできることから取り組んでいくための行動を提案していくものであり「自立」に向かって成長する子どもの育成を図る上で目安となるものです。
具体的な行動指針は、主に次の4つに分類され6つの行動モデルから成り立ちます。
このような内容からも、子ども育成条例には市民協働の行動指針がしっかりと策定されていることがわかります。子どもたちを取り巻く環境は一人一人大きく異なり、私たち大人の子ども達への思いもさまざまです。
ですので、一人一人が今の立場からみて必要と思われる「行動指針」を実行していくことが必要なのです。
岡山市は、未来の希望である子どもたちの自立のために様々な取組を進めています。行動指針は市民が日々取り組んでいくことですが「行動計画」は岡山市が取り組んでいく施策です。
具体的には主に8つの支援事業に分類されます。
情報の提供及び交流による子育て支援・・親子のふれあい促進などに取り組みます
| 心豊かな岡山っ子応援団事業 |
| のびのび親子広場事業 |
学校園及び教職員のパワーアップ支援・・学校の特色に応じた教育環境の充実を図ります
| 地域協働学校推進事業 |
| 学力・授業力アップ支援事業 |
| 教職員研修事業 |
| 学校支援ボランティア |
| 放課後こども教室推進事業 |
| 安全・安心ネットワーク推進事業 |
子育てに優しい事業者の表彰を行う
| 少年リーダー養成事業 |
| 子ども体験活動促進事業 |
| 教育相談室運営事業 |
| 子ども相談主事配置事業 |
| 地域での子育て支援ネットワークづくりの推進 |
| 広がる教育の輪ー広報・広聴活動の充実事業ー |
| 子育て支援事業の提供 |
このように家庭・学校・地域・事業それぞれの分野において、しっかりとした支援と事業施策における行動計画が立てられていることがわかります。
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
岡山市中区は、市民協働で「自立」に向かって成長する子どもを育成していくことを目指していることがわかりました。岡山っ子育成条例の制定により、家庭・学校園・地域社会・事業者それぞれが果たすべき責務を持ち、そして市がその行動計画を立て全体的な支援を行なうという連携が取れています。
子ども達の望ましい成長を見守り支えられる支援事業の存在は、子どもたちの教育を進める上で心強いことと言えます。
岡山市中区は、市民協働で自立する子どもを育成し、子ども達が健やかに成長するために必要なことを大人達が共有できる取組を行なっている自治体と言えます。
家庭教師のやる気アシストは岡山市中区の不登校や発達障害のお子さんや勉強に困っているお子さんのサポートをしています。
対象の学年は小学1年生から高校3年生です。無料の体験授業も行っていますので、少しでも興味を持って下さった方はこのページをご覧いただけますと幸いです。