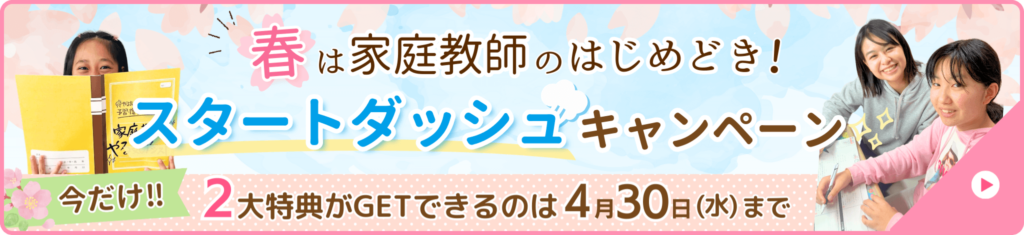この記事は以下のサイトを参考にしています。
https://uminoko.jp/for-children/biwako-floating-2days/
びわ湖フローティングスクールとは滋賀県が学生を対象に行っている体験学習です。
学習船「うみのこ」に乗船して、びわ湖やふるさと滋賀について様々な体験学習を通して学ぶことができます。
この記事ではびわ湖フローティングスクールの日程や、学習内容などを紹介していきます。
目次
滋賀県の学習船「うみのこ」での2日間の日程
1日目
STEP
10:00 出港・開校式・オリエンテーション
開校式はフローティングスクールの入学式です。
心を込めて『希望の船』を歌います。
STEP
11:00 避難訓練・展望活動
万が一があったときの避難経路の確認と、湖上から見える様々な島や湖岸の様子を展望します。
STEP
12:00 昼食・船内見学
昼食は、和風焼魚定食です。
ますの塩焼きをはじめ、びわ湖の幸がいっぱいです。
STEP
14:00 寄港地活動
寄港地の歴史や文化、自然環境の様子に着目しながらウォークラリーや散策を行います。
STEP
17:00 夕食・シャワー
夕食は、「湖の子」ステーキディナーです。
近江牛のステーキが食べられます。お米は近江米で、環境のことを考えて作られています。
2日目
STEP
6:00 起床・洗面
朝早く起きることは健康にも脳にもいいことがたくさんあります。
STEP
7:15 朝食・朝の集い
朝食は、セルフメイドサンドイッチです。
ソーセージとハムには、滋賀県産の豚肉が使われています。
STEP
8:50 びわ湖学習
びわ湖について様々なことを勉強します。詳しくは次でまとめています。
STEP
12:00 昼食・学習のまとめ
昼食は、「湖の子」カレーです。
滋賀県産のぶた肉を使ったカツカレーで、「うみのこ」の名物です。
STEP
14:00 閉校式・下船
学習船「うみのこ」で勉強したことをこれからに活かしていきましょう!
フローティングスクールでの学習内容
フローティングスクールでは、「びわ湖」を通して様々なことを学ぶことができます。
ここではどんなことを学ぶかを紹介していきたいと思います。
- 水中カメラ探検
びわ湖の湖底の様子を水中カメラのライブ映像で見ることができます。湖底の観察では、これから観察する生き物や水の様子を確かめたり、港による湖底の違いを比べたりします。びわ湖で泳ぐ魚が見られるかもしれません。
- 衛星写真シート検索
滋賀県の衛星写真シートを広げ、地形や川、水源の山など、琵琶湖を中心とした滋賀県の様子を見ることができます。学校や自分の家を見つけてみましょう。
- 生き物ふれあいコーナー
魚や貝、水草、エビなど観察する対象に触れて調べることができます。観察は水の中で行います。観察の後は石けんでよく手を洗いましょう。
- デジタル図鑑で調べもの
観察や実験をするとき、生き物の名前や特徴を調べることができます。画面にタッチするだけで簡単に操作できます。
- 専門家からのお話
デジタル図鑑にある動画で専門家からの話を聞いて、考えをさらに深めましょう。うみのこに乗船している児童のみなさんに向けた1分程度のお話です。
- ヨシペンで絵画
船内のヨシペンを使って、絵具で思い出の景色や観察した生き物を描きます。事前にハガキと切手、送り先の住所と宛名を準備しておけば、寄港地からハガキを投かんすることもできます。
- 湖底の観察
湖底から泥や砂れきをとって、湖底にいる生き物や、湖底の環境などについて調べます。
- びわ湖の生き物ワークショップ
今のびわ湖の様子や課題から、これからのびわ湖についてグループで話し合います。
- 魚の放流体験(県水産課連携事業)
湖魚を放流し、びわ湖の保全と再生について考えます。
- カッター活動
力をあわせてオールをこいで、びわ湖を身近に感じます。
- 深層水と表層水の比較
びわ湖の深い所の水と表面の水を比べてみよう。びわ湖の深呼吸と生き物の関わりについて考えよう。
- 手旗活動
手旗での通信を体験します。
- びわ湖の魚の採捕(さいほ)体験
かごあみをしかけて魚をつかまえます。種類や形の違いを調べ、びわ湖の生態系について考えます。
- 貝の観察
うみのこ給食で食べるシジミや湖底からとった貝を題材に、びわ湖固有の貝や生き物について考え、シジミを使ったストラップやマラカスを作ります。
- 水のよごれ回復実験
よごれたびわ湖の水がどれぐらいで元通りになるか、実験を通して考えます。
- びわ湖の食文化
「湖の子」給食に使用されている滋賀県産の食材や琵琶湖八珍について調べることで、郷土の食文化を学び、生活とびわ湖との関わりについて考えます。
- びわ湖の水の透視度調査
びわ湖各所の透視度を調べ、びわ湖の水のにごりと人間の生活とのつながりについて考えます。
- ヨシの活用
ヨシの役割や水質浄化作用について学び、実物のヨシに触れ、びわ湖と人々の生活のかかわりについて考えます。
- ロープワーク
船の生活には欠かせないロープワークに挑戦します。環境や用途に応じた結び方があることなど、船内生活の知恵や文化について考えます。
- 湖岸の水生生物観察
びわ湖岸からの滋賀・びわ湖の様子を展望したり、水生生物を調べたりすることで、びわ湖周辺の生き物と水のかかわりについて考えます。
- びわ湖の漁業
「たつべ」や「もんどり」といった本物の漁具に触れたり、漁の映像を視聴したりしてびわ湖の漁法について考えます。
- プランクトンの観察
びわ湖各所の水をプランクトンネットででとり、顕微鏡でプランクトンを観察します。
- 水草の観察
びわ湖にある水草をとり、種類や特徴、水草の問題について考えます。観察したら水草の標本を作ってみます。
- 水鳥の観察
湖岸や甲板から水鳥の様子を観察し、冬のびわ湖にすむ水鳥のようすや特徴について調べます。
滋賀県が考える船の教育的機能
船は人を鍛える
船という限られた機能・空間の中では、絶えず工夫と忍耐が要求される。この環境下での生活は、便利な日常生活に馴れ過ぎた人に、生活の原点を考えさせ、自らを厳しく鍛え、たくましい気力と体力を育てる。
船は規律を教える
船という小社会の中で楽しく有意義な生活を送るためには、自己の欲求を抑制し、規律を守ることが必要となる。また、生命を守るために、船長やリーダーの判断や指示に絶対従わなければならないこともある。規律が自己や他者を束縛するものではなく、自分や仲間を生かすためのものであるということを明確に認識させる。
船は心と心を通わせる
船は、初めて出会う人と気持ちよく挨拶を交わしたり、話したりして自然と交流を深めることができるという不思議な力を持っている。そして、人との出会いが印象的となり、それぞれの立場を尊重し合いながら、自らを高めさせる。
船は人の視野をひろげる
海や湖から見る景色は、陸上での見馴れた景色とは違ったものを語りかけてくる。遠くかすむ山々、海岸・湖岸や島々の様子、またそこに生きる生物たちなど、視点移動する船から周りを見つめることは、たとえ見馴れたものであっても新鮮な感動を呼ぶ。それは自分や自分の生活、また故郷などを新たに見つめ直す機会となり、人の思考の範囲を広げ、深める。
船は「夢とロマン」を与える
海や大きな湖は、それを見る人のまだ見ぬ世界へのあこがれや、冒険心をかきたてる。また、はるかかなたへ人や物を運ぶ船は、人の活動範囲・限界点を一気に跳躍させるという点で、人に限りない「夢とロマン」を与え続けてきた。船は、特に青少年に自らの将来を切り拓いていこうとする気概を持たせる。
滋賀県で勉強に困っている保護者さま・お子さんへ
滋賀県が行っているびわ湖フローティングスクールについて紹介してきました。
課外活動では普段学校で勉強しないことや地域について考えるきっかけになるのでとてもいいですよね。
家庭教師のやる気アシストは滋賀県で「定期テストや入試・受験対策に強い」家庭教師として、小学1年生から高校3年生のお子さんを対象に、ご自宅に伺い勉強の指導を行っています。
少しでも興味を持って下さった方はこのページをご覧いただけますと幸いです。
家庭教師のやる気アシスト – 定期…
滋賀県で家庭教師をお探しなら|受験勉強、成績アップ、テスト対策に強い家庭教師です。 – 家庭教師のやる…
滋賀県で定期テストで点数が取れないお子さん、平均点以下のお子さん、勉強のやり方が分からないお子さんでも、1対1指導の家庭教師のメリットを生かし、お子さんと二人三脚…