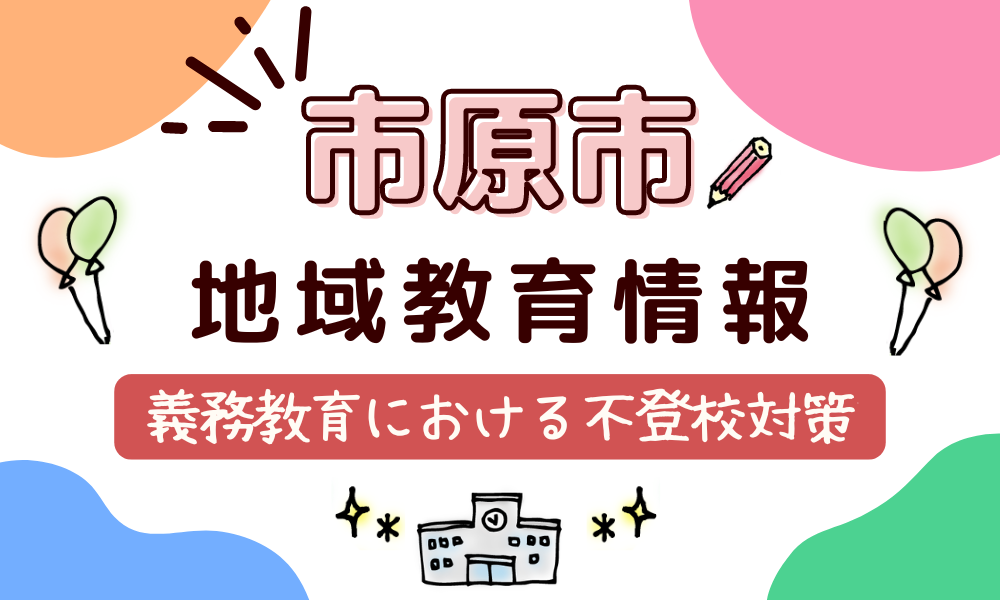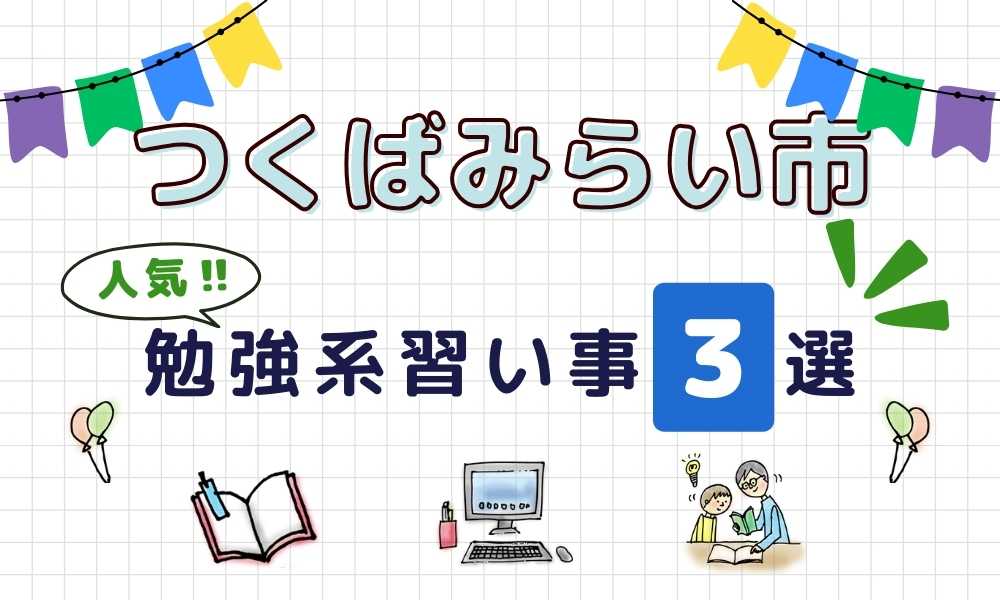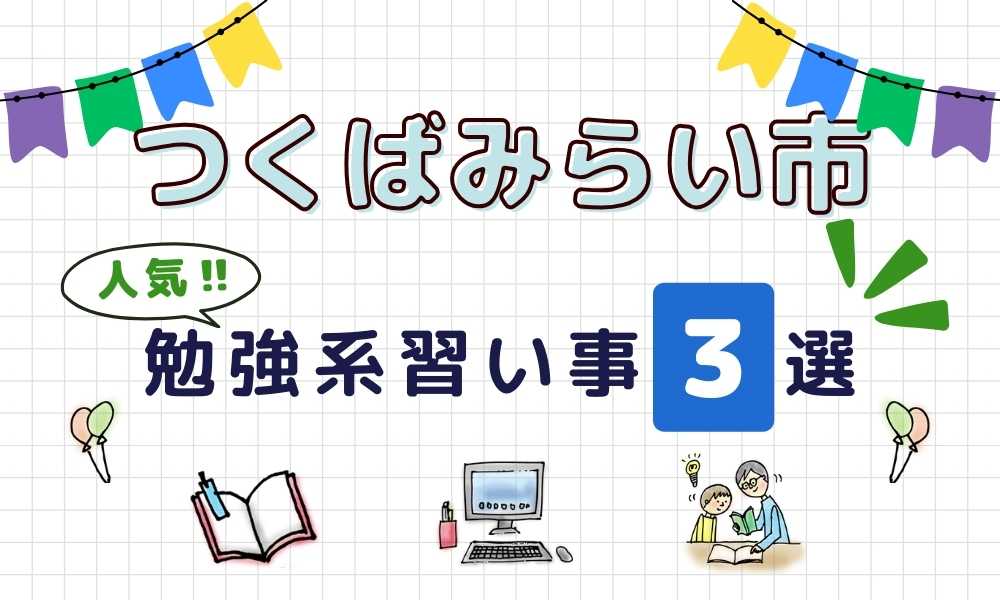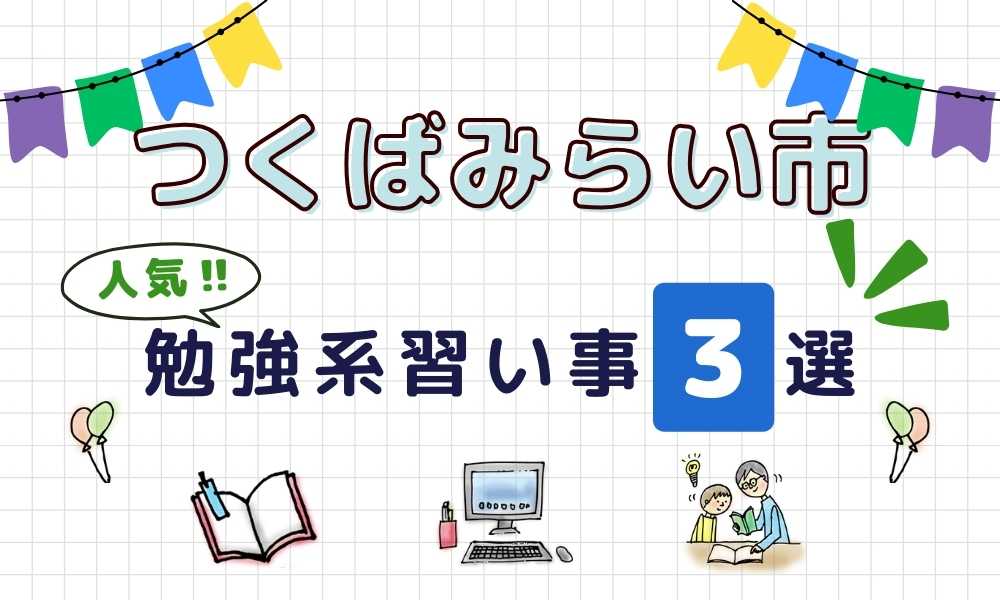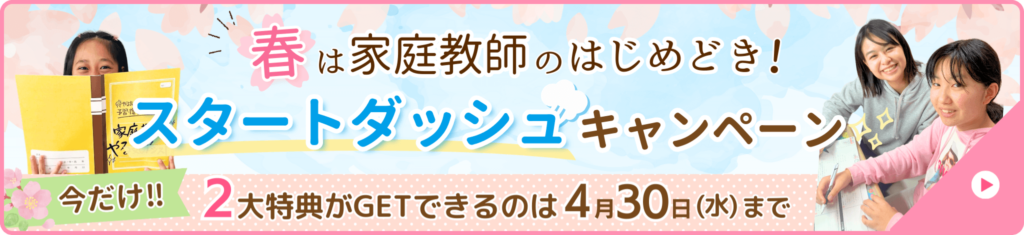





この記事は以下のサイトを参考にしています。
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoikuiinkai/1044685/1009232/1029300/1043076.html
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoikuiinkai/1002552/1026823/1026916.html
宝塚市では、子どもの豊かな育ちと学びを創造するためには、宝塚市民が一丸となって教育活動に取り組むことが必要であると考えています。
今回は宝塚市が策定した教育振興基本計画とコミュニティスクールについて紹介します。
宝塚市では、これまで教育委員会と学校・家庭・地域が手を携えて、子どもたちの心身を健やかに育むためのさまざまな事業を行ってきました。
しかし、近年問題視されている学校でのいじめ問題や教職員問題、子どもたちの人権意識の醸成や体力づくり、ICT機器を活用した教育の実践など、今後重点的に取り組むべき課題が山積しています。
このような背景から策定された第2次宝塚市教育振興基本計画は、令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)までの10年間を期間として定めており、子どもたちの心身の健全な発達と社会教育の振興のために尽力し、基本目標の達成へ向けた施策の展開を進めています。
宝塚市の基本目標
― 自分を大切に、人を大切に、ふるさと宝塚を大切にする人づくり -
宝塚市の基本目標にある「自分を大切に」とは、自分の命・自分の存在を大事に思うこと、「人を大切に」は自分と同じように他者の命も大切にし、その存在を大事に考えるという意味があります。また、「ふるさと宝塚を大切にする人づくり」は、自分を育ててくれた故郷(宝塚市)の自然や建物・文化・伝統に感謝の気持ちを抱き、人や物を大切にする心を育みたいということを表します。
宝塚市ではこの目標を達成するために、学習指導要領※など国の方針を踏まえ、子どもたちの「生きる力」を育む取組を進めています。
全国のどの学校でも一定の水準が保てるように、文部科学省が定めている教育課程(カリキュラム)の基準を指す。
およそ10年に1度改訂していて、子どもたちの教科書や時間割は学習指導要領の基準を基に作られている。
宝塚市教育振興基本計画では、「子ども・教育環境・地域・生涯学習」の各視点から、10年間を見通した4つの教育の方向性を定めています。
宝塚市では、人間の基礎作りとなる幼児教育に重点を置き、保育所(園)や認定こども園、小・中学校との連携を図って教育を進めています。
技術革新が進展している中で子どもたちの「生きる力」を育むために、学力の基礎基本を身につけるための教育の実施、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を進めます。また、安全・安心な学校給食の提供や、中学校における部活動のあり方の見直しなど、子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう取り組んでいます。
他にも、子どもの感性を育むため積極的に読書活動を取り組み、読書本来の楽しさを感じられる、適切な言葉で自分の思いを伝えられる子どもを育てます。全ての子どもたちに寄り添い、向き合い、理解しながら、子どもたちの育ちを支援します。
子どもたちの学力向上や健全な身体、豊かな心の育成のためには、学校園と教職員の教育力向上が必要不可欠です。
宝塚市では、教員同士が切磋琢磨し授業力を高め合う仕組みや研修を充実させ、教員の業務負担軽減と勤務時間の削減に取り組んでいます。子どもと向き合う時間を確保し、人材育成や学校園組織における運営体制の強化に努めます。
また、教員が風通しの良い中で連携して子どもたちを見守り、力を合わせて学校園での課題の解決に取り組めるような環境づくりを進めます。私立の学校園の適正規模及び適正配置についても検討し、子どもたちが安心して学校に通えるような学校環境の整備を推進します。
子どもたちの学びは、学校だけでなく家庭や地域、あらゆる場面を通じて行われています。学校・家庭・地域が連携し多様な学びの機会の提供するなど、地域一丸となった支援が重要です。体験学習や地域人材による指導の機会を増やし、子どもの育みを支援していきます。
日本では、基本的な方針の一つに「障害学び、活動できる環境を整える」ことを示しています。
人生100年時代を迎えた現代、宝塚市では市民が気軽に学ぶことができるように、公民館や図書館などの社会資源を充実させ、情報の提供や学びの機会拡大に努めます。また、文化遺産の保存継承や活用に努め、市民の文化意識向上を目指すとともに、スポーツ施設の整備・イベントの開催・団体などと連携してスポーツ活動の活性化を図ります。
子どもの豊かな育ちと学びを創造するためには、学校・家庭・地域の人々が目標を共有し、一丸となって教育活動に取り組むことが重要です。
宝塚コミュニティ・スクールでは、学校と地域の人々が「地域でこんな子どもを育てたい」という「めざす子ども像」に向かって、地域のTAKARA(宝)である子どもを育てるため学校運営に参画することを目指しています。
コミュニティスクールとは「学校運営協議会」を設置している学校のことを指し、2022年度から宝塚市内の小中特別支援学校全校に導入しています。
学校運営協議会の役割としては、学校長が作成する学校運営の基本方針の承認、学校運営について教育委員会や学校長と意見交換、教員の任用に関して教育委員会規則に定める事項について意見交換、などがあります。
学校長や教員の異動があっても、学校運営協議会によって地域との組織的な連携・協働体制がそのまま継続可能です。
学校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して、学校や地域、子どもたちが抱える課題に関係者全てが当事者意識をもち、「役割分担をもって連携・協働による取組」ができます。
学校運営協議会を通して、子どもたちがどのような課題を抱えているのか、地域でどのような子どもを育てていくのか、何を実現していくのかという「目標・ビジョン」を共有できます。
子どもにとってのメリット
教員にとってのメリット
保護者にとってのメリット
地域の人々にとってのメリット
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
今回は宝塚市の教育振興基本計画とコミュニティスクールについて紹介しました。学校と地域の人々が「このような子どもを育てていきたい」という共通目標を持ち、一丸となって学校運営に参画していることが分かりましたね。
家庭教師のやる気アシストは、宝塚市で「定期テストや入試・受験対策に強い」家庭教師として、小学1年生から高校3年生のお子さんを対象に、ご自宅に伺い勉強の指導を行っています。
少しでも興味を持って下さった方はこのページをご覧いただけますと幸いです。