
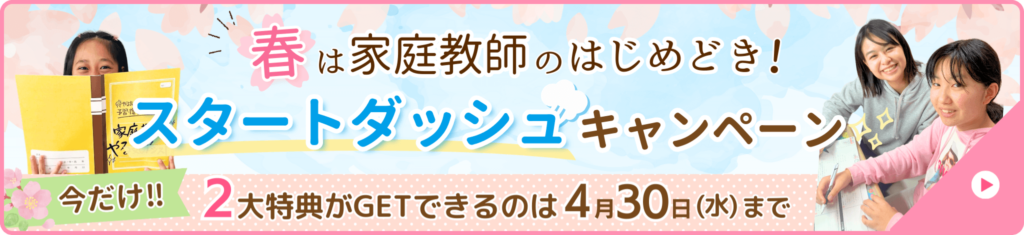





さて、今回から「化学」の分野を学んでいきたいと思います。
実験器具の説明から、身の回りの物質についてを学んでいきたいと思います。
有機物や無機物の違いや、プラスチックや金属などの性質も見ていきます。
この章では実験器具について学んでいきます。
具体的には
の3種の器具について学んでいきます。
ガスバーナーは物質を加熱するときに用いる器具です。ネジが二つあり、それぞれ「ガス」と「空気」を調節します。どちらがそのネジかを問う問題はよく出るのでしっかり押さえていきましょう。
上にあるのが「空気調節ネジ」、下にあるのが「ガス調節ネジ」です。”上空”と覚えると覚えやすいです。
火をつけるまでの手順を紹介していきます。
てんびんにはいろんな種類がありますが、ここでは「電子てんびん」と「上皿てんびん」について学んでいきます。
まず「電子てんびん」を紹介していきます。
「電子てんびん」は物質の”質量”を図るために使います。普段のなじみのある”体重”とは異なるので注意が必要です。
違いは”体重”は重力が加味されますが、”質量”が考慮されないことが違います。
そのため、ド〇ゴンボールの重力室に入って10倍の重力を掛けても”質量”は変わらず、”体重”が変わります。
手順としては
次に「上皿てんびん」を紹介していきます。
「上皿てんびん」は「分銅」を載せていき、「つりあい」を利用して物質の質量を調べたり、必要な量の物質を図るときに使います。
つりあいとは指針の左右の振れ幅が同じときのことを言います。
手順としては
メスシリンダーは液体の体積を図るときに使います。
体積は、液体や気体なら「ml」や「l」、固体なら「cm³」を用いて表します。1mlは1cm³になるので覚えておきましょう。
手順としては
この章から本題の身の回りの物質について見ていきましょう。
この章では「有機物」と「無機物」について学んでいきます。
この二つは炭素があるものが有機物、炭素が無いものが無機物と教科書では書いてあります。
実はこの説明だけだと不十分です。性質を見ながら確認していきたいと思います。
「有機物」の物質は加熱をすることによって、燃えたり・焦げたりします。
また、炭素と酸素が結びつくことによって二酸化炭素が排出されます。
二酸化炭素が発生しているかどうかを確認するためには有名な性質があります。
それは石灰水と二酸化炭素を入れて振ると石灰水が白く濁るという性質です。これはずっと出てくるのでしっかり覚えておきましょう。
それでは身近な物質を「有機物」と「無機物」に分けていきましょう。
| 有機物 | 無機物 |
| 砂糖 ろう 木 紙 エタノール プラスチック | ガラス 鉄・スチールウール アルミニウム 食塩 炭素 二酸化炭素 |
さて、矛盾が発生しましたね。
教科書通りなら炭素があるのが有機物ですが、炭素と二酸化炭素は無機物に分類されます。??って感じですね。
結論からお伝えします。
「有機物」とは炭素と”水素”を含む物質のことを言います。
加熱をした時に二酸化炭素だけでなく、少量でも水が発生します。良く出題される引っかけ問題なのでしっかり押さえておきましょう!
ここでは身近な有機物の例としてプラスチックについて紹介していきます。
1980年代から色々なものに使われるようになり、いまは身の回りの様々なものがプラスチックで出来ています。
性質としては、水に浮くこと、燃えると二酸化炭素を排出することが挙げられます。
それでは種類ごとに紹介していきます。
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
ここでは身近な無機物の例として金属について紹介しています。
アルミ缶に使われるアルミ、コインに使われる銅、ネジに使われる鉄などが有名です。
金属は独自の性質などがあり、よくテストにも出てくるのでここで押さえておきましょう。
金属には大きく4つの性質があります。
※磁石にくっつくには鉄など一部の金属なので注意してください。



