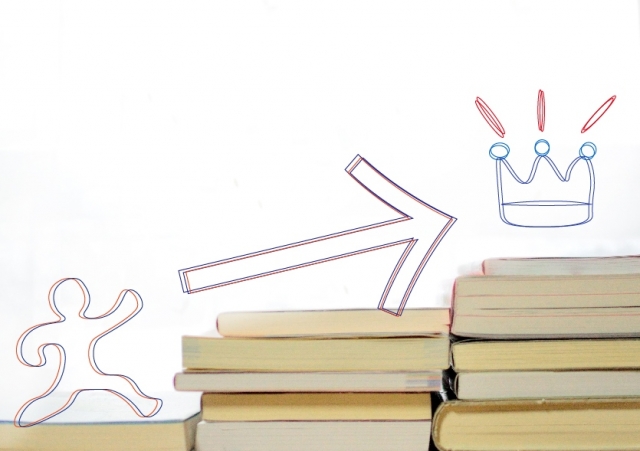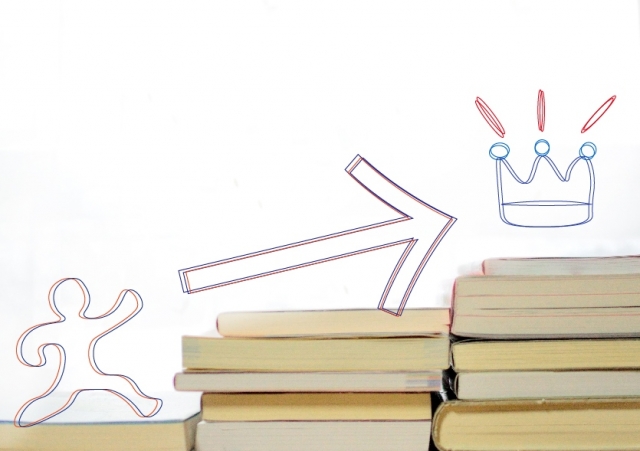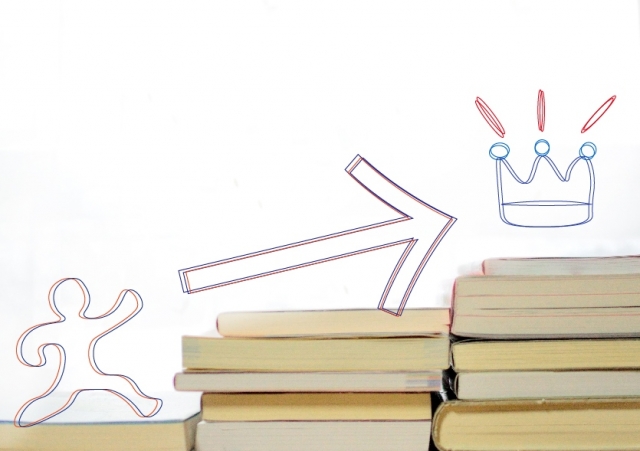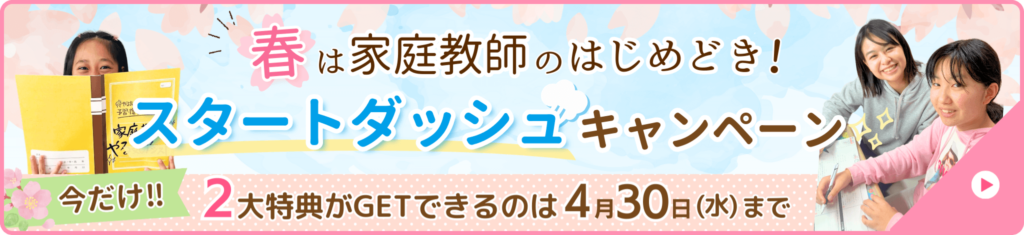





普段接している文章に注目してみましょう。
文章とは文字通り文がたくさん集合したものです。
その文は文節で区切ることができ、さらに単語に区切ることができます。
ここでは、文節同士の関係や、よく出てくる単語の紹介などをしていきます。
冒頭部分でもお話しましたが、普段私たちが何気なく使っている言葉や文章。これを法則性を元に解体・分類していきたいと思います。
そのような文を司る法則を「文法」と呼びます。
第一弾として言葉の単位から見て参りましょう!
文章:いくつかの文が集まってできた、ひとまとまりの内容。
段落:文字を意味のまとまりごとに区切ったもの。形式段落と意味段落の2種類があります。
文 :「。(句点)、!(感嘆符)、?(疑問符)」で区切られた意味のまとまり。
ここからが本題です。
文をもっと小さな単位に分解してみましょう。
文を発音や意味が不自然にならないように短く区切ったまとまりのことを「文節」と呼びます。
その「文節」をさらに、意味のある言葉の最終単位に区切ったものを「単語」と呼びます。
それでは早速問題を解いてみましょう。
以下の分を文節に分けよ。
①佐藤先生の授業は分かりやすい。
②洪水で橋が流される。
③私がこの写真を撮りました。
文節に分けるときのヒントは「ネ」をつけて区切っていくことです。実際にやってみると以下のようになります。
①佐藤先生の(ネ)/授業は(ネ)/分かりやすい。
②洪水で(ネ)/橋が(ネ)/流される。
解けましたか?
さて最後の問題ですが、実は少し難易度が上がります。
③を「私が(ネ)/この写真を(ネ)/撮りました。」とした人は多いかと思います。
しかし、これは4文節の言葉なんです。
「あの、この、こと、もの、とき」は必ず文節が区切られます。「あの子の事と物、時々思いだす」と覚えておくと良いでしょう。
上記を踏まえて再度問題を見てみましょう。
③私が(ネ)/この(ネ)/写真を(ネ)/撮りました。
が正解です。
発展的内容ですが、文節を区切る意味は、これから単語や品詞ということを学んでいくのですが、その下準備です。
文節が切れるタイミングにある言葉の種類を「自立語」と呼びます。そして「自立語」についている言葉を「付属語」と呼びます。
自立語とは簡単に言うと、それだけで意味が通じる言葉です。「先生」「洪水」「流す」「撮る」「この」などはこれだけでもひとつの言葉として成立しています。
一方付属語は、それだけでは意味が通じない言葉です。「の」「は」「で」などはこれだけでは言葉として成立していませんね。
具体的に例題1の①~③を単語で区切ってみましょう。(自)が「自立語」、(付)が「付属語」です。
①佐藤先生(自)/の(付)/授業(自)/は(付)/分かりやすい(自)
②洪水(自)/で(付)/橋(自)/が(付)/流さ(自)/れる(付)
③私(自)/が(付)/この(自)/写真(自)/を(付)/撮り(自)/ました。(付)
見比べると、文節の数と自立語の数は必ず一致することが分かります。
文節同士の関係には大きく4つの関係があります。この4つの関係を通称「文の成分」と呼びます。
また、上記の4つの成分に加えて、「連文節」という二つ以上の文節がまとまるときにのみ出てくる2つの関係を合わせた6つの関係を押さえていきましょう。
主語・述語の関係は基本的に以下4つのパターンで表されます。
①~が【主語】—どうする【述語】
(例)雪が/とける。兄が/運転する。
②~が【主語】—どんなだ【述語】
(例)空が/青い。彼女は/正直だ。
③~が【主語】—なんだ。【述語】
(例)あれが/火星だ。私が/代表だ。
④~が【主語】—ある・いる・ない【述語】
(例)本が/ある。ペンが/ない。
※主語は「~が」だけでなく、「~は」「~も」「~こそ」などが主語になったり、省略が行われたりもするので注意が必要です。
修飾・被修飾の関係は「どのように」「どのくらい」「いつ」「どこで」「誰と」「何を」など、他の文節を詳しく説明したり、内容を補ったりする働きがあります。
また、用言(動作や状態を表す言葉)を修飾するものを連用修飾語、体言(生物や事柄などを表す言葉)を修飾するものを連体修飾語と呼びます。
(例)風が/強く/吹く。8時に/起きる。
接続の関係は文や文節をつなぐ働きを持った「接続語」とそれを受ける文節との結びつきのことを言います。
(例)雨が/降りそうなので、/今日の/練習は/中止に/します。
独立の関係は他の文節とは直接関係を持たず、独立している「独立語」とそれ以外の文節との結びつきのことを言います。
(例)うん、/わかったよ。
二つ以上の文節がまとまったものを連文節と呼びます。
この時上記の2-1~2-4での文の成分の呼び方が若干変わります。
また、これから学ぶ2-5,2-6の関係が出てきます。
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
二つ以上の文節が対等に並ぶときの関係のことを並列の関係と呼びます。
(例)母も/姉も/賛成だ。
主な意味を表す文節と、意味を補う文節の関係のことを補助の関係と呼びます。
(例)妹が/歌って/いる。