
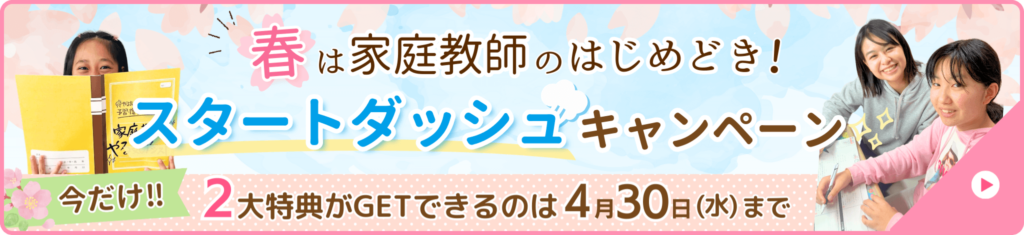





地方自治について解説していきます。
定期テストなどで出題されると困る単元の一つだと思いますが、覚えることはそこまで多くありません。一つ一つ確実に抑えることを意識して頑張りましょう。
地方自治とは、地域・地方の運営を、そこの住民の意思に基づいて行うことをいいます。
カンタンに言えば「自分が住む町の事は自分たちで決めていくぞ!」ということです。
国政では「日本全体として決めるべき事・解決すべき課題」や「外国との関係」などスケールの大きい政治問題に対処します。
一方で、県や市町村といった地方公共団体は「地域特有の課題の解決」「地域の強みを活かした行政」「住民一人ひとりに寄り添った行政の実施」など、それぞれの地域の住民が感じ取りやすい内容の行政を行っています。
地方自治のしくみは国政のものと違う点が多いので、しっかり覚えていきましょう。
国に内閣総理大臣と呼ばれるトップがいるように、各地方公共団体にも首長と呼ばれるトップがいます。例えば、県のトップは県知事、市のトップは市長といったようなものです。
彼らはその地域の住民による直接選挙で選ばれます。内閣総理大臣は国民からの選挙で直接選ぶことができないので、大きな違いの一つといえます。
国に国会と呼ばれる議会があるように、各地方公共団体にも地方議会があります。例えば、府の議会であれば府議会、町の議会であれば町議会と呼ばれます。
議会議員はその地域の住民による直接選挙で選ばれます。国会議員も国民による直接選挙なので、選挙制度については同じようなものであると言えます。
議会では、その地域の予算(お金の使い道)を決めたり、条例をつくったりします。条例はその地域のみで適用されるきまりで、法律の範囲内で作られます。
例えば「路上喫煙禁止」みたいな看板を街で見かける地域に住んでいる方がいれば、それが条例で決められていたりします。他にも「迷惑防止条例」という、暴力、ちかん、ストーカーなど様々な迷惑行為に対して罰則を与える条例が全国の地方公共団体にあります。
首長と議会はお互いに制し合う事が出来るように制度が設けられています。
まず、首長は議会に対して「議会で決まったことの拒否権」「議会の解散権」ができます。
議会は首長に対して「首長の不信任決議」ができます。不信任決議とは、議員の多くが「首長が私たちの町のリーダーとしてふさわしくない」と判断した時に、議会で多数決を取り、それを表明することができるというものです。不信任決議が可決された(2/3の議員が出席して3/4以上の賛成が得られた)とき、首長は
のどちらかをしなければいけないと決まっています。
財政というのは国・公共団体の歳入(収入)や歳出(支出)のことです。
国は財政によって、国民の福祉や国の根幹となるインフラ(国道・橋)の建設・保守の為にお金を使っています。要するに、国全体の問題に対処する事柄に対して歳出しているわけです。歳入については、国民が給料をもらった時や、ものを買った時に税金として得ているのです。
地方公共団体も運営するためには歳入が必要で、それらによって地方行政が行われています。
各地方公共団体では、地方税というものを定めて、歳入を得ています。地方税には
というような直接税(税を納める人と税金を負担する人が同じ税)や、
というような間接税(税を納める人と税金を負担する人が別の税)が課されています。
これらによって得られたお金によって地方公共団体は運営しています。
地方公共団体のほとんどは、これら地方税のみでは足りないという状況にあります。その理由は「少子高齢化」「都市集中による住民の減少」といったものですが、この不足を埋めるために様々な補助・借金があります。
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
住民の私達も様々な形で地方公共団体の政治に参加することができます。
主な参加方法として選挙、直接請求があります。
各地方自治体に住む住民は、その地域の首長・議会議員を選挙によって選ぶことができます。
選挙への参加は国政と同じく18歳以上の住民全員が投票することができます。
また、住民は首長や議員になりたい時に立候補することができます。
都道府県知事は30歳、それ以外(市町村の首長、地方自治体の議会議員)は25歳でなることができます。
ちなみに、議会議員に立候補するためには「立候補する地域にある程度の期間住んでいる」必要があります。一方、首長にはそれらはありません(例えば、大阪府知事や市長の選挙に奈良や兵庫に住んでいる人が立候補することができる、ということです)。
国政と大きく違い、直接政治に関わる方法として直接請求があります。各地域に住んでいる人々は、以下の場合に多くの住民の署名(賛成)によって様々な物事について請求する権利があり、それを直接請求権といいます。議会を通さずに進められることが大きなポイントです。
住民が「こんな条例が必要!」「この条例は時代遅れだからいらない!」と思った時に、その地域の有権者(18歳以上の市民)の50分の1の署名を集めることで、首長に是非を求めることができます。請求先は首長になります。
住民が「この人は私たちの地域のリーダーとしてふさわしくない!」と思った時に、有権者の3分の1の署名を集めることで、住民投票を行うように求めることができます。住民投票の結果過半数が賛成となれば、その首長・議員を辞任(リコール)させることができます。直接請求によって住民投票を行いたいので、請求先は選挙管理委員会になります。
住民が「この議会はまともに機能していない!また選挙して選び直したい!」と思った時に、有権者の3分の1の署名を集めることで、住民投票を行うように求めることができます。住民投票の結果過半数が賛成となれば、その首長・議員を辞任(リコール)させることができます。リコールと同様に、請求先は選挙管理委員会になります。



